●「日常生活の指導」で何をしたらいいのかわからない
●「朝の会」をどのようにしたらいいか迷っている

こんにちは,元特別支援学級担任のサンプです
日常生活の指導の授業の一つ「朝の会」について書きたいと思います
「朝の会」おすすめポイント
〇1年間を通して繰り返し行うため,子どもたちがやり方を完全にマスターすることができる
〇プログラムに児童一人一人の実態に応じた課題を含めることができる
〇広範囲に教科等の内容を含むことができる
〇「各教科等を合わせた指導の特徴と留意点」をピッタリふまえている
この記事はサンプ自身が行った個人的実践ですが,少しでもお役に立てれば幸いです
PR
日常生活の指導
「日常生活の指導」とは,生活単元,遊びの指導,作業学習とともに「各教科等を合わせた指導」という指導形態の一つです
以下,文科省の「特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編(小学部・中学部)」から抜粋です
第4章 第2節
3 指導の形態について
(3)各教科等を合わせて指導を行う場合
【各教科等を合わせた指導の特徴と留意点】
ア 日常生活の指導
日常生活の指導は,児童生徒の日常生活が充実し,高まるように日常生活の諸活動について,知的障害の状態,生活年齢,学習状況や経験等を踏まえながら計画的に指導するものである。
日常生活の指導は,生活科を中心として,特別活動の〔学級活動〕など広範囲に,各教科等の内容が扱われる。それらは,例えば,衣服の着脱,洗面,手洗い,排泄,食事,清潔など基本的生活習慣の内容や,あいさつ,言葉遣い,礼儀作法,時間を守ること,きまりを守ることなどの日常生活や社会生活において,習慣的に繰り返される,必要で基本的な内容である。
日常生活の指導に当たっては,以下のような点を考慮することが重要である。
(ア)日常生活や学習の自然な流れに沿い,その活動を実際的で必然性のある状況下で取り組むことにより,生活や学習の文脈に即した学習ができるようにすること。
(イ)毎日反復して行い,望ましい生活習慣の形成を図るものであり,繰り返しながら取り組むことにより習慣化していく指導の段階を経て,発展的な内容を取り扱うようにすること。
(ウ)できつつあることや意欲的な面を考慮し,適切な支援を行うとともに,生活上の目標を達成していくために,学習状況等に応じて課題を細分化して段階的な指導ができるものであること。
(エ)指導場面や集団の大きさなど,活動の特徴を踏まえ,個々の実態に即した効果的な指導ができるよう計画されていること。
(オ)学校と家庭等とが連携を図り,児童生徒が学校で取り組んでいること,また家庭等でこれまで取り組んできたことなどの双方向で学習状況等を共有し,児童の充実を図るようにすること。
これを読んでみてどうですか?
1回で理解した人はいるかもわかりませんが,私は正直わけがわかりませんでした😓
「で?何やったらいい?」で,先輩から学んだのが「朝の会」でした
PR
「朝の会」とは
通常学級では,よく10分程度で朝の会が行われています
でもそれは「授業時間」には含まれていないはずです
日常生活の指導として行うこの朝の会は,学級の実態に合わせてプログラムを考え,1時間かけて「授業」として行います
日常生活の指導で行う「朝の会」は,先程書いた「各教科等を合わせた指導の特徴と留意点」をふまえたものです
朝の会 実践例
子どもたちの成長とともに少しずつ内容をアップデートし,いくつかパターンを変えてやっていました
まずは1年生が多い学級のような最初のパターンは次のようなものです
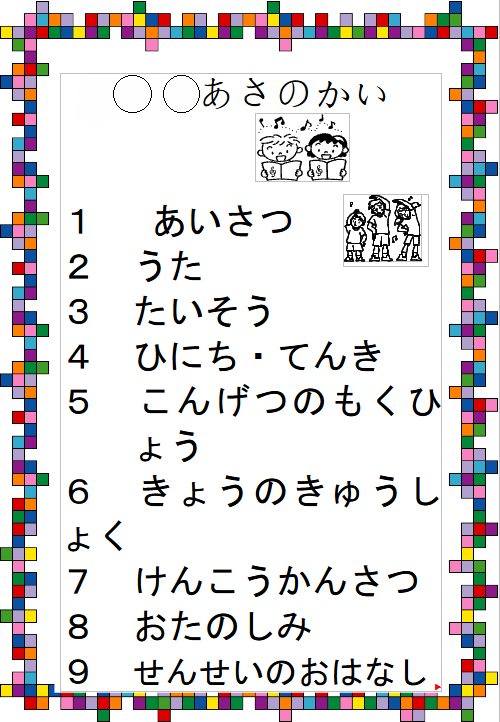
(word文書をA3サイズに印刷し,ラミネート加工して掲示しておきました)
- 1.あいさつ
 日直
日直1ばん,あいさつです
おはようございます みんな
みんなおはようございます
日直の合図で朝の挨拶をします
- 2.うた
 日直
日直2ばん,うたです
各学校でよく取り組まれている「今月の歌」を,CDの歌に合わせて一緒に歌います


- 3.たいそう
 日直
日直3ばん,たいそうです
主にラジオ体操をやっていました

- 4.ひにち・てんき
※前日,または朝の会までに担当の児童(日直)があらかじめ月日,天気カードを黒板に貼っておきます
 日直
日直4ばん,ひにち・てんきです
さん,はい!黒板などに書いてある月日,天気カードを見ながら,みんなで一斉に言います
 みんな
みんな「きょうは〇がつ〇にち○ようびです!」
「きょうのてんきは〇〇です!」 - 5.こんげつのもくひょう
 日直
日直5ばん,こんげつのもくひょうです
さん,はい! みんな
みんな※ 例)そとでげんきにあそぼう!
学校で決められた生活目標を一斉に言います
- 6.きょうのきゅうしょく
 日直
日直6ばん,きょうのきゅうしょくです
給食の献立表を見て,ひとつひとつ日直が言った後,他の児童が繰り返して言います
 日直
日直ぎゅうにゅう
 みんな
みんなぎゅうにゅう!
 日直
日直ごはん
 みんな
みんなごはん!
・・・・
という感じです

- 7.けんこうかんさつ
 日直
日直7ばん,けんこうかんさつです
(元気な時)
みんなでひとりずつ児童の名前を呼び,呼ばれた児童は「はい!げんきです!」と手を挙げて言います(言葉が出ない児童は挙手だけでもいい) 日直
日直さん,はい!
日直がこう言わないと出だしがそろわない
 みんな
みんな〇〇 〇〇くん!
 〇〇〇〇くん
〇〇〇〇くんはい! げんきです!
返事の後,みんなで拍手

順番は出席番号順など,わかりやすく固定しているものがいいです
(元気でない時)
名前を呼ばれた児童は「はい,〇〇(病名,ケガ名など)です」と手を挙げて言います 日直
日直さん,はい!
 みんな
みんな〇〇 〇〇くん!
 〇〇〇〇くん
〇〇〇〇くんはい,〇〇(病名,ケガ名など)です
 みんな
みんなおだいじに~
返事の後,みんなは「お大事に」と言います
- 8.おたのしみ
 日直
日直8ばん,おたのしみです
かんたんなレクレーション,読み聞かせ・・・など,主に担任が行います

ここまで時間がかかり過ぎていたり早すぎたりしていたら,ここで時間調整します
- 9.せんせいのおはなし
 日直
日直9ばん,せんせいのおはなしです
せんせいおねがいします日によって話す内容は様々ですが,主に1時間目からの学習,交流学習,行事など今日の予定を伝え,一日の見通しを持てるようにしました

〇初めの段階や言葉が出にくい児童が日直の場合などは教師が一緒に進行役となり,進めていきます
〇「1.あいさつ」
声がでる者は,子どもも先生もいっしょに元気よく声を出しましょう
〇「2.うた」
歌が苦手な児童,声が出にくい児童がいる場合は先生(担任,補助の先生)でひっぱって歌いましょう
しかしこういう私は歌が苦手で,歌わない子どもたちばかりだとここで一気に盛り下がりました😓
〇「3.たいそう」
ラジオ体操を1年中やるのはさすがに難しかったので,第2体操に変えたりストレッチ体操にしたり「ロングブレス体操」を取り入れたりしました
〇「4.ひにち・てんき」
お天気マークはイラストを印刷してラミネート加工したものに磁石を貼って黒板に掲示しました

私の場合,「〇がつ〇にち」の数字部分と「〇ようび」の「げつ~きん」の部分もあらかじめ印刷しておいたものを黒板に貼らせていました
〇「5.こんげつのもくひょう」
毎日,合言葉のように繰り返し唱えるとだんだん覚えていきます
〇「6.きょうのきゅうしょく」
元いた学校では毎月給食の献立表を全児童に配布していました
各教室にも掲示してあり,それを使いながら進めました
担任によっては,献立の一つ一つの絵を黒板に貼っていくようにさせる指導もあります

そしてもう一つ
先程の献立表を児童一人一人にコピーして持たせておき,前日の給食の振り返りを記入させました
このことについても詳しくはいずれ別記事で書きたいと思いますが,給食の食べ残し,偏食等の改善にたいへん効果がありました
〇「7.けんこうかんさつ」
拍手を受けるのがうれしくて,少々調子が悪くても子どもは「げんきです」と言う傾向があります
調子が悪い日の方が少なく言い方がわかりにくいという理由もあると思われます
どう言えばいいのかは指導が必要です
〇「8.おたのしみ」
慣れてくると7番のけんこうかんさつまであっという間に進み,時間が30分以上余るようになります
そうなると「おたのしみ」に費やすネタもいろいろと工夫するか,プログラムを増やすようにしていかないといけません
〇「9.せんせいのおはなし」
次の時間に体育がある場合,「せんせいのおはなし」時間の中で着替えの時間をとりました
その他にも鉢植えの水やり,生き物のエサやり,ロッカー・荷物の整理,宿題直し・・・など「せんせいのしじ」として時間を有効に使いました
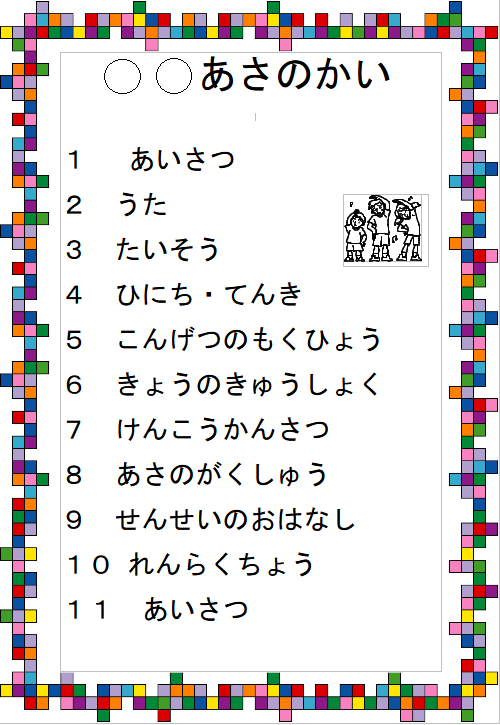
文字の読み書きが進んできたころ「パターン2」へ変更しました
➡「8.おたのしみ」に代えて「8.あさのがくしゅう」を入れました
➡「10.れんらくちょう」「11.あいさつ」を加えました
- 1.あいさつ
- 2.うた
- 3.たいそう
- 4.ひにち・てんき
- 5.こんげつのもくひょう
- 6.きょうのきゅうしょく
- 7.けんこうかんさつ
- 8.あさのがくしゅう
主として宿題の直しをしました
直しが早く終わった児童や直しのない児童は,復讐プリントなどをします
直しが終わったプリント類は,穴あけパンチで穴をあけさせ,ファイルに閉じるようにさせました
- 9.せんせいのおはなし
- 10.れんらくちょう
文字を書けるようになった児童は,自分で翌日の連絡帳を書かせました
まだ書くことができない児童は,「ゴム印」などを使って記入させました
「ゴム印」についてはいつか別記事で触れたいと思います
- 11.あいさつ
「パターン1」では,朝の会を終わるあいさつを書いていなかったので付け加えました
〇「8.あさのがくしゅう」
以前のパターンでは着替え,鉢植えの水やり,生き物のエサやり,ロッカー・荷物の整理などの時間を確保していませんでしたので,このプログラムの中でしました
本音を言うと「おたのしみ」を続けるのがしんどくなったという理由もあります😓
〇「10.れんらくちょう」
教科名など毎日書いているとよく書けるようになります
自分で予定を書くので,子どもが一日の見通しをもつのにも役立ちます
朝の会ができなかったときなどでも,必ず自分で書かせるようにしました
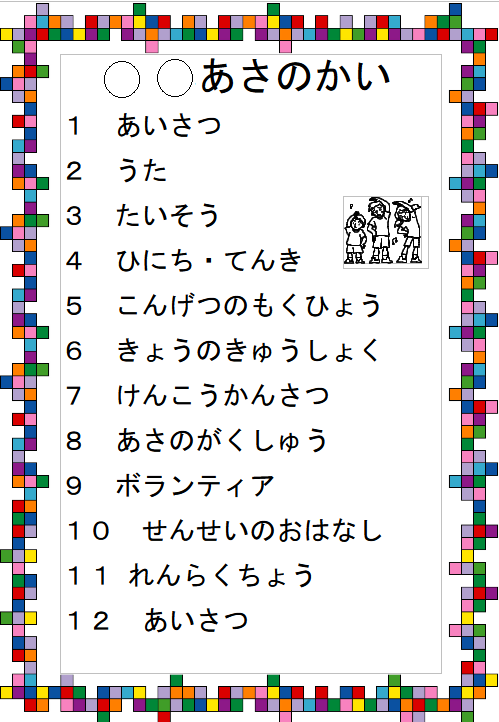
➡「9.ボランティア」を加えました
- 1.あいさつ
- 2.うた
- 3.たいそう
- 4.ひにち・てんき
- 5.こんげつのもくひょう
- 6.きょうのきゅうしょく
- 7.けんこうかんさつ
- 8.あさのがくしゅう
- 9.ボランティア
高学年になってきたので,学校の草取りなどのボランティア活動を始めました

- 10.せんせいのおはなし
- 11.れんらくちょう
- 12.あいさつ
〇「9.ボランティア」
大げさなものでなくていいので,草取りやごみ拾いなど少しの時間だけやりました
私の反省点として,こちらから一方的な指示でやらせてしまったことです
できれば子どもたちの意思を尊重するのがいいと思います
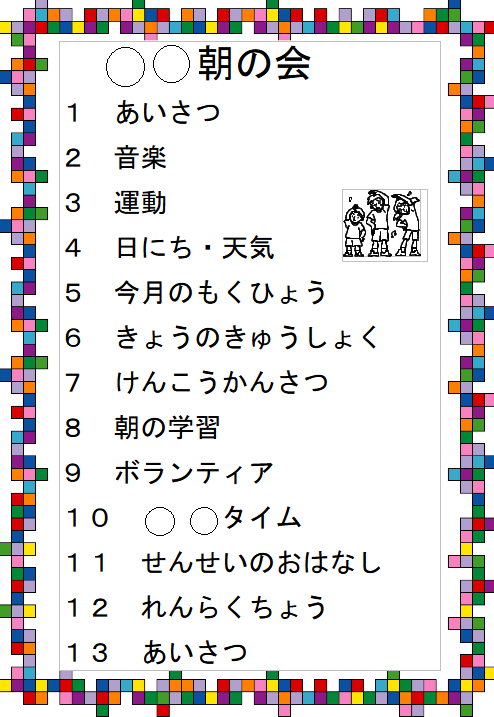
漢字表記を増やしました
➡「2.うた」のかわりに「2.音楽」にしました
➡「3.たいそう」のかわりに「3.運動」にしました
➡「10.〇〇タイム」を加えました
- 1.あいさつ
- 2.音楽
歌だけでなく,鍵盤ハーモニカやリコーダーの練習もできるように「音楽」としました

- 3.運動
なわとびやジョギングなど,体操以外に体を動かす活動を入れました

- 4.日にち・天気
- 5.今月のもくひょう
- 6.きょうのきゅうしょく
- 7.けんこうかんさつ
- 8.朝の学習
- 9.ボランティア
- 10.〇〇タイム
以前の「おたのしみ」のような学級みんなで活動する内容を入れました

- 11.せんせいのおはなし
- 12.れんらくちょう
- 13.あいさつ
〇「2.音楽」
特別支援学級の子どもたちは,鍵盤ハーモニカやリコーダーなどの練習をなかなか家でできないことが多かったです
交流授業だけでは身に着かないので,楽器を練習する時間をこの中に含めました
〇「3.運動」
【パターン4】になったころに「くねくね体操・がにがに体操」を取り入れました
すると子どもたちが楽しそうにやるだけでなく,いろいろな効果が出ました
詳しくはいずれ記事を書きます
〇「10.〇〇タイム」
以前の「おたのしみ」の新バージョンです
学級全員で行うみんなの時間です
なんでもできる時間にしました
ただ「パターン4」ではプログラムが増えすぎて時間がなくなってしまい,しばしば省略することになってしまったのが課題です
「朝の会」と各教科等との関連
各教科等との関連を書いています
指導計画を立てる時,参考にしてください
【あいさつ】
・生活科「オ人との関わり」
【うた】
・音楽科
【たいそう】
・体育科
【ひにち・てんき】
・生活科「サ生命・自然」
【こんげつのもくひょう】
・生活科「ケきまり」
【きょうのきゅうしょく】
・特別活動「学級活動」
【けんこうかんさつ】
・体育科「G保健」
【おたのしみ】
・生活科「エ遊び」など(内容により関連多数)
【せんせいのおはなし】
・生活科「日課・予定」
【あさのがくしゅう】
・各教科
【れんらくちょう】
・国語科
・生活科「日課・予定」
【ボランティア】
・道徳
【〇〇タイム】
・各教科等
まとめ
日常生活の指導で「朝の会」は,全国の特別支援学級,特別支援学校で実施されているのではないかと思います
ただこう言ってはなんですが,毎日同じ繰り返しという性質からか,あまり授業にメリハリや派手さがないため,研究会や研究授業ではめったに目にすることがありませんでした
以前自分が探した範囲では,あまり書籍も出版されていなかったと思います
そのため「朝の会」のやり方を知ったのは特別支援学級担任14年目になってからでした
それから自分なりにアレンジして今回のパターンを作りました
現在の特別支援学級の先生方がこれを参考にしてよりいいものにしていただけば幸いです
(広告)
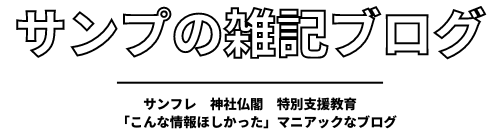

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/413a854f.a410f474.413a8550.b5561809/?me_id=1251035&item_id=22069802&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2F8760000%2F8759715.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


